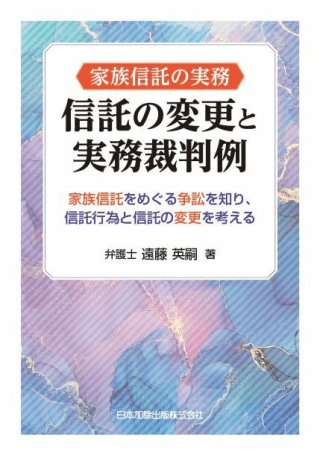所長 信託造語 集
支援付き意思決定と意思決定支援義務
本文は、令和6年9月14日に実施された、東京大学市民後見人養成講座の修了生に対する令和6年度市民後見人フォローアップ研修における、挨拶である。
皆さん、お早うございます。令和6年度市民後見フォローアップ研修の開始にあたり、一般社団法人地域後見推進センターの理事長をしております、遠藤から、一言ご挨拶申し上げます。
本研修には、220名を超える修了生からご参加いただきありがたく思っています。
私ども、一般社団法人地域後見推進センターは、すべての地域において、地域後見が達成されるように組織されたものです。その一環として、この地域後見を担う市民後見人の養成に取り組んでいます。
地域後見とは、本人(成年被後見人等、任意後見契約の委任者)が住む市町村(地域)、そして後見人が活動する地域の支援(地域力)を得て、後見人が後見活動を適正に行い、これにより本人の権利が擁護され、そして本人がその地域に包摂されて普通の生活を送ることができるという仕組みができ上ることです。
そのためには、各地に地域後見センターである中核機関ができて、市民後見人も、親族後見人も、本人を支えてゆく仕組みができ上ることを目指しています。
ところで、ご承知のように、さまざまな課題を抱えている、成年後見制度が、よりよい制度になるように、本年6月から、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において、成年後見制度の改正論議が始まり、白熱した議論がなされております。
すでに、7回ほど、会議が開催されているようでありまして、争点に関する考え方が、それぞれの委員から開陳され、さらに関係団体の方々のヒアリングも行われています。
これまでの検討の中で、主に法定後見の開始に際して考慮すべき事柄や、法定後見の終了に関する事柄について検討がなされ、その中で、現行後見・保佐において事理弁識能力が回復しない限り終わらない制度であったものを変えていく、という方向では意見が一致したと言われています。しかしながら、後見の終了に関し、期間満了で当然に権限喪失する仕組みには検討の余地があるとし、期間を定めるのではなく終期や終了事由を定めた方がよいのではないか、などさまざまな意見が出でいるようであります。
この内容については、午前中の講師であります、山野目章夫先生から詳しいお話があると思います。
ここで私が触れておきたいのは、本人の意思尊重義務などに違反している場合の、成年後見人の解任、交代の問題です。今にち、本人の支援付き意思決定(意思決定支援)は、成年後見制度では最も重要視されている事柄です。かつては、ベストインタレス・最善の利益を確保するということが、言われてきましたが、今は変わったということです。
ところで、意思尊重義務は民法858条に根拠がありますが、意思決定支援義務となると、どうでしょうか。
支援付き意思決定(意思決定支援)の法的根拠は何でしょうか、皆さんお判りでしょうか。
AIの答えは、意思決定支援の法的根拠は、日本国憲法第13条や、障害者権利条約12条2項・3項が挙げられるというのです。
しかし、これでは、意思決定支援義務違反を問おうとしても、法律家の成年後見人には、「その根拠は何か」と、逆に問われて、結果、逆襲に遭いそうです。
この辺の法的根拠となる、改正論議はどうなのかと、気になるところです。
これを、任意後見契約で考えてみますと、後見契約であれば、契約条項に意思尊重義務と同様に、意思決定支援義務を契約条項に定めることはできるのではないかと思います。そして、それを履行しない場合は、一種の善管注意義務(民法644条)の違反として、後見人の解任事由にしたり、損害賠償責任を負うとするのが、理にかなっているように思うのですが。
さて本日は、山野目先生のほか、厚労省の火宮麻衣子成年後見制度利用促進室長から、新しい動きを紹介していただけることになっていますし、愛知県大府市の杉浦様や、13期修了生の山下さんからは、地域後見にかかわる話をいただけることになっています。
本研修は、改正論議の最も身近な、しかも皆さんがぜひ聞きたい、知りたいという、事柄について、講師の先生方からご講義があるはずです。
十分有意義な研修になると思いますので、しっかり学んでほしいと思います。
この発言にある『後見は遺言を破る』というのは、家族信託の紹介の中で、破られない遺言の説明として登場していることがらである。
成年後見人が、被後見人に遺言があってもお構いなしに、将来相続財産になる不動産を換価処分してしまうことから、その防御のために家族信託を登場させるというものだが、ここにきて、後見人の方も、意思決定支援が叫ばれる中で、ようやく、財産承継に関する本人意思の尊重に目覚めたのかなと思い、この後見は遺言を破ることがあってはならないということを再確認した次第である。
8050は遅い 7040まだ大丈夫
この「8050」の問題は、「80」代の高齢の親が、「50」代の自立できない子どもの生活を支えるという問題です。背景にあるのは、障害を有するいわゆる「親亡き後問題」ですが、最近では子どもの「ひきこもり問題」 も取り上げられています。
私は、親亡き後問題は、家族信託契約で解決するという考えを持っています。むろん、親御さんが80歳代でも判断能力が十分であれば、公正証書は作成できます。しかし、最近お会いする人の中には、支援疲れなのでしょうか、まだら症状の人も少なくないので、もっと早く相談していただければよかったのにと思う事例も少なくありません。
家族のための信託は、特異で、難しいので、やはり70歳台の決断力がしっかりしているときに、相談して公正証書は作成しておくべきです。
かかる相談者の多くは、自分の生活や福祉をしっかり確保しなければならないということを忘れています。親亡き後問題については、すべてを総合的の考えていただくには、認知機能低下後は難しいと考えてほしいのです。
私の成年後見・任意後見に対する思い ‼
東京大学 市民後見人養成講座 修了式における、私の挨拶です。いま、私が、成年後見制度の再構築に願う気持ちです。
令和5年3月18日
主催者側を代表してご挨拶申し上げます。
第15期生の皆様、研修に汗を流しこれが実り、本日の修了の日を迎えられた111名の方々、誠にお目出とうございます。私は、一般社団法人地域後見推進センターの理事長遠藤です。
本修了式に当たっては、全員の方ではありませんが、最後の最後に、リアル参加を得て、なむけの言葉を申し上げることができ、感無量です。コロナ禍にあって、しかも中にはコロナの洗礼を受けながら、所期の目的を達成された受講生の皆さん、そのご努力に対しまして、先ず敬意を表しますとともに重ねてお祝い申し上げます。
皆さんが、受講された研修項目や実習については、後に学事報告で説明があろうと思いますが、私共は、市民後見人養成講座では、これ以上の人材を集めることがむずかしいと思われる先生方を、講師陣に迎えて、取組みさせていただきました。その先生方のご尽力に対しても、御礼を申し上げたいと思います。
皆様も実感されているとおり、内容も、学問的なことがら、実践にわたる深みのある内容を提供させていただいたと思っています。ここで学んだことを、これから仕事のなかで、またさまざまの社会生活の中で生かしてほしいと思います。
ところで、本講座で学んだとおり、成年後見制度は大きな転換期にあります。
令和5年3月18日
主催者側を代表してご挨拶申し上げます。
第15期生の皆様、研修に汗を流しこれが実り、本日の修了の日を迎えられた111名の方々、誠にお目出とうございます。私は、一般社団法人地域後見推進センターの理事長遠藤です。
本修了式に当たっては、全員の方ではありませんが、最後の最後に、リアル参加を得て、なむけの言葉を申し上げることができ、感無量です。コロナ禍にあって、しかも中にはコロナの洗礼を受けながら、所期の目的を達成された受講生の皆さん、そのご努力に対しまして、先ず敬意を表しますとともに重ねてお祝い申し上げます。
皆さんが、受講された研修項目や実習については、後に学事報告で説明があろうと思いますが、私共は、市民後見人養成講座では、これ以上の人材を集めることがむずかしいと思われる先生方を、講師陣に迎えて、取組みさせていただきました。その先生方のご尽力に対しても、御礼を申し上げたいと思います。
皆様も実感されているとおり、内容も、学問的なことがら、実践にわたる深みのある内容を提供させていただいたと思っています。ここで学んだことを、これから仕事のなかで、またさまざまの社会生活の中で生かしてほしいと思います。
ところで、本講座で学んだとおり、成年後見制度は大きな転換期にあります。
数年後には、この制度が大きく変わっているかもしれません。我が国の現状を見た場合、人口の減少、高齢者の増加、歯止めのかからない認知症患者の増加、少子化対策の必要性、どれをとっても、今までと同じ考えで取り組んだとしたら、成年後見制度はますます毛嫌いされる制度になるような、さまざまな問題をかかえているのです。
この制度については、今、まさに、誰でもが利用してよかったという制度に代える必要があるのです。
この制度については、今、まさに、誰でもが利用してよかったという制度に代える必要があるのです。
そのために、平成28年に成年後見制度利用促進法を成立させ、後見人の利用促進の議論がなされてきました。ここには、その関係者の方々も、ご参加いただいているので、申し訳ないのですが、促進策が見えてきたという実感がありません。そもそも、私が知る関係する委員の中には、当初、「利用促進の委員会は、そもそも後見制度の利用者を増やそうという議論をする場所ではない」と言い、また、「本人が後見人を選ぶ任意後見制度は、ここで議論する考えはもうとうない」と、私には考えられないことを言う先生いたので、議論をしても、使える制度改正が実現できるのか心配していました。
しかしながら、そんな中でも、厚生労働省を中心とした政府の方々のご努力もあり、地域の後見センターになる「中核機関」の設置や、また「地域後見連携ネットワーク構想」が真剣に議論されて、次第に、地方における後見センター構築に向けて動き出したのです。この「中核機関」の構想などは、地域後見そのもので素晴らしいものです。
私どもも、すべての市町村に、ネットワークに支えられた中核機関ができれば、私どもが目指している「地域後見」が実現できると、大いに期待したわけです。しかしながら、このコロナ禍にあって、事実上、退潮しかけない状況になってしまったわけですが、地域後見の実現のためにも、この中核機関構想を続行し必ず全国に構築してほしいと思っています。その場合、そこには、必ず市民後見人だけでなく親族(家族)後見人をも、包摂してほしいと思っています。
それに、第一次基本計画では、あまり議論されなかった、任意後見制度も、今次計画は取り上げられておりますので、これが、これからの議論の中心になることを期待しているところです。
少し長くなりますが、持論を披歴させてもらいます。
成年後見制度の基本は一つです。「(この制度によって)支援が必要な人を護る」ということです。このことは忘れてはなりませんが、ただいま一つ、私が申しあげたいのは、“この「要支援者を支援する人も支援すること」も大事だということです。要は「地域で働く後見人」をも守ることも不可欠なのです。それは、家族後見人、そして市民後見人ですが、これらの後見人をも守るのが、これからの”地域における後見制度だ”と思っています。
ところで、新聞等でも報道されていますように、成年後見制度は大きく変わるという動きが出ています。これは、法務省が中心となって、商事法務研究会において、「成年後見制度の在り方に関する研究会」での議論に関するものです。
承知の方も多いかも知れませんが、ここで、成年後見制度の課題としてあげられているのは
● 一度、成年後見制度の利用を開始すると、本人が亡くなるまで辞められない
● 後見人の途中交代は難しく、最初に決まった人物が継続する
● 親族が後見人に就くことが難しい
という問題があり、その解決に向けて、
❶ 本人にとって必要な時に、必要な範囲でのみ利用できる制度とする
❷ すでに成年後見制度を利用している人について、一定期間ごとに本当に後見制度が必要な状態か、見直す機会を設ける
❸ 柔軟に後見人を交代できるようにする
ことが可能か、などが議論されています。この研究会で取り上げられているのは、いわゆる限定後見(スポット後見)ですが、ここで考えていただくのは、専門職による後見が終わっても、可能な限り成年後見制度を終了させずに、家族後見人、そして市民後見人に引き継いでほしいということです。専門職による後見が終了したとしても、本人を護ることは必ず残るのです。無碍に放り出すことはしないでほしいということです。
今一つ、大事なことがあります。
成年後見制度は、これを利用する人の意思、意見が尊重されることが必要です。ただし、今議論されている、本人の意思決定支援の問題とは、別のことも考えるべきです。もちろん、本人の意思は最も尊重されるべきです。それをも前提に、成年後見制度を利用する人、この人とは、誰でしょうか。裁判所をはじめ、専門職後見人には、本人しか、見えていません。しかし、考えてみてください、任意後見制度の場合は、本人から、後見人として選任されて、さまざまな情報や本人の考えを聴取し、その考えを実現しようとしているのは、任意後見人です。それを考えると、任意後見人の意思は基本的には本人意思と同視できるものです。この者は、その本人意思を実現するために、任意後見人となったものです。その点は、親族後見人も同じです。本人意思を実現するために、成年後見制度を選び、自らが、後見人になっているのです。
しかるに、現状を見た場合、これらの人が意見(声)を出しても、多くの場合、認められません。それでよいのでしょうか。
私の願いは、この「これを利用する人の意思、意見が尊重されること」です。今、これを利用しようとする多くの国民はこのことを求めているのではないでしょうか。この任意後見人や家族後見人の考え、意見を無碍(むげ)に否定することは正しいこととは思えません。ここでも、本人意思を確実に実現できる、親族(家族)後見人を重用してほしい、それから、市民後見人を活用してほしいということです。
このように、成年後見制度の利用促進を図るには、これからは本人意思実現可能な任意後見制度を中心に、利用のシフトを替えることも大事なことだと思います。もちろん、任意後見制度にもあい路があります。任意後見監督人選任の申立てをしないということです。これは、任意後見監督人の「監督」とその「報酬」の問題でもあります。その報酬を恐れて、任意後見の開始をためらっている人が多いわけですが、その解決策はあるはずです。任意後見監督人の報酬を低くし定額にする、あるいは保険が利用できるようにする、ということです。介護保険がつかえるのであればよいのですが、無理でしょうから、何らかの保険制度、例えば生命保険の特約として「成年後見・任意後見利用」の項目を設けて、入院や通院特約と同じような対応でまかなえるようにする、そしてその中で任意後見制度利用補償保険については優遇税制を導入するとか、一定幅の所得控除を認めるなど、さらなる利用促進策はあるはずだと思っています。
今日の社会、さらにこれからの社会を見た場合、「高齢者が高齢者を護る社会」、そして「高齢者が子供を護る社会」が、一層深化、深まって行きます。そのような中で、成年後見制度もまた大きく変わるはずです。変わらないと、困る、そのように思っています。そして、誰でもが利用してよかったという制度に代わってほしいのです。
成年後見制度は大事な制度です。そこで、皆さんには、ここで学んだ成年後見制度につき、これからも常に新しい情報を得て学び直し、真に自分のもの、知識にしてほしいと願っています。そして、皆様の仕事の上で、また生活の上で、学んだことを生かしてほしいと思います。
皆様のご活躍を祈念し、私の祝辞といたします。本日は誠にお目出とうございます。
しかしながら、そんな中でも、厚生労働省を中心とした政府の方々のご努力もあり、地域の後見センターになる「中核機関」の設置や、また「地域後見連携ネットワーク構想」が真剣に議論されて、次第に、地方における後見センター構築に向けて動き出したのです。この「中核機関」の構想などは、地域後見そのもので素晴らしいものです。
私どもも、すべての市町村に、ネットワークに支えられた中核機関ができれば、私どもが目指している「地域後見」が実現できると、大いに期待したわけです。しかしながら、このコロナ禍にあって、事実上、退潮しかけない状況になってしまったわけですが、地域後見の実現のためにも、この中核機関構想を続行し必ず全国に構築してほしいと思っています。その場合、そこには、必ず市民後見人だけでなく親族(家族)後見人をも、包摂してほしいと思っています。
それに、第一次基本計画では、あまり議論されなかった、任意後見制度も、今次計画は取り上げられておりますので、これが、これからの議論の中心になることを期待しているところです。
少し長くなりますが、持論を披歴させてもらいます。
成年後見制度の基本は一つです。「(この制度によって)支援が必要な人を護る」ということです。このことは忘れてはなりませんが、ただいま一つ、私が申しあげたいのは、“この「要支援者を支援する人も支援すること」も大事だということです。要は「地域で働く後見人」をも守ることも不可欠なのです。それは、家族後見人、そして市民後見人ですが、これらの後見人をも守るのが、これからの”地域における後見制度だ”と思っています。
ところで、新聞等でも報道されていますように、成年後見制度は大きく変わるという動きが出ています。これは、法務省が中心となって、商事法務研究会において、「成年後見制度の在り方に関する研究会」での議論に関するものです。
承知の方も多いかも知れませんが、ここで、成年後見制度の課題としてあげられているのは
● 一度、成年後見制度の利用を開始すると、本人が亡くなるまで辞められない
● 後見人の途中交代は難しく、最初に決まった人物が継続する
● 親族が後見人に就くことが難しい
という問題があり、その解決に向けて、
❶ 本人にとって必要な時に、必要な範囲でのみ利用できる制度とする
❷ すでに成年後見制度を利用している人について、一定期間ごとに本当に後見制度が必要な状態か、見直す機会を設ける
❸ 柔軟に後見人を交代できるようにする
ことが可能か、などが議論されています。この研究会で取り上げられているのは、いわゆる限定後見(スポット後見)ですが、ここで考えていただくのは、専門職による後見が終わっても、可能な限り成年後見制度を終了させずに、家族後見人、そして市民後見人に引き継いでほしいということです。専門職による後見が終了したとしても、本人を護ることは必ず残るのです。無碍に放り出すことはしないでほしいということです。
今一つ、大事なことがあります。
成年後見制度は、これを利用する人の意思、意見が尊重されることが必要です。ただし、今議論されている、本人の意思決定支援の問題とは、別のことも考えるべきです。もちろん、本人の意思は最も尊重されるべきです。それをも前提に、成年後見制度を利用する人、この人とは、誰でしょうか。裁判所をはじめ、専門職後見人には、本人しか、見えていません。しかし、考えてみてください、任意後見制度の場合は、本人から、後見人として選任されて、さまざまな情報や本人の考えを聴取し、その考えを実現しようとしているのは、任意後見人です。それを考えると、任意後見人の意思は基本的には本人意思と同視できるものです。この者は、その本人意思を実現するために、任意後見人となったものです。その点は、親族後見人も同じです。本人意思を実現するために、成年後見制度を選び、自らが、後見人になっているのです。
しかるに、現状を見た場合、これらの人が意見(声)を出しても、多くの場合、認められません。それでよいのでしょうか。
私の願いは、この「これを利用する人の意思、意見が尊重されること」です。今、これを利用しようとする多くの国民はこのことを求めているのではないでしょうか。この任意後見人や家族後見人の考え、意見を無碍(むげ)に否定することは正しいこととは思えません。ここでも、本人意思を確実に実現できる、親族(家族)後見人を重用してほしい、それから、市民後見人を活用してほしいということです。
このように、成年後見制度の利用促進を図るには、これからは本人意思実現可能な任意後見制度を中心に、利用のシフトを替えることも大事なことだと思います。もちろん、任意後見制度にもあい路があります。任意後見監督人選任の申立てをしないということです。これは、任意後見監督人の「監督」とその「報酬」の問題でもあります。その報酬を恐れて、任意後見の開始をためらっている人が多いわけですが、その解決策はあるはずです。任意後見監督人の報酬を低くし定額にする、あるいは保険が利用できるようにする、ということです。介護保険がつかえるのであればよいのですが、無理でしょうから、何らかの保険制度、例えば生命保険の特約として「成年後見・任意後見利用」の項目を設けて、入院や通院特約と同じような対応でまかなえるようにする、そしてその中で任意後見制度利用補償保険については優遇税制を導入するとか、一定幅の所得控除を認めるなど、さらなる利用促進策はあるはずだと思っています。
今日の社会、さらにこれからの社会を見た場合、「高齢者が高齢者を護る社会」、そして「高齢者が子供を護る社会」が、一層深化、深まって行きます。そのような中で、成年後見制度もまた大きく変わるはずです。変わらないと、困る、そのように思っています。そして、誰でもが利用してよかったという制度に代わってほしいのです。
成年後見制度は大事な制度です。そこで、皆さんには、ここで学んだ成年後見制度につき、これからも常に新しい情報を得て学び直し、真に自分のもの、知識にしてほしいと願っています。そして、皆様の仕事の上で、また生活の上で、学んだことを生かしてほしいと思います。
皆様のご活躍を祈念し、私の祝辞といたします。本日は誠にお目出とうございます。
受益者代理人は、本当に受益者のための代理人か!
受益者代理人は、その名のとおり受益者の代理人であるが、家族信託では二つの役割をもっていると言われている。
受益者にとっては、信託という制度の中で難しい意思表示を要する事項につき自分を代理してくれるものである。
一方、受託者にとっては、監督者であるが、信託を快く思っていない受益者がいる場合には、受益者側の立場にあるものの、信託の目的達成のため公平公正な立場から信託事務を円滑に処理する上での受託者の理解者ともなるとされている。
実務ではどうかというと、8割方、後者の円滑な事務処理のために活躍してもらっていると言っても過言ではないようである。
委託者が願望する「信託の目的」を達成するためには、受益者において受託者に協力して受益を受けるというのが、実際の信託の構造である。受益者代理人は、そのような構造の上に立っており、それを直視した場合、それは、受益者の代理人なのかという疑問もあろう。しかしながら、信託の基本は、「信認関係」である。家族のための民事信託では、そもそも対立構造のもとでは、信託は機能しないということだろう。
これは、委託者代理人についても言えるのだろう。委託者の言うことを聞く代理人だと言っても、消えてもらう人の声は、この信認関係には無力なのではないか。
空き家特例が家族信託で適用されない! 「実家信託」はだめになったのか
最近、信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得に関し、特別控除の特例の適用はないという東京国税局の文書回答があった。
案件は自益型の信託契約で、母Aが所有する居住用家屋等を、受託者である子Bに信託譲渡し、Aが信託財産から利益を享受する受益者となった。この契約では、受益者の死亡により信託は終了し、居住用家屋等は相続人である帰属権利者のBとCの両名に給付された。
両名は、当該居住用家屋等を相続のあった年の翌年に売却したが、この譲渡について、空き家控除の要件である「相続又は遺贈により」(相法9の2④)、被相続人居住用家屋等の取得をした相続人に該当するから、空き家控除の適用があると考えるとして東京国税局に照会を行った。
しかし、東京国税局は、①信託の終了による財産の移転は単なるみなし規定で、「相続」や「遺贈」に該当せず、空き家控除の条文には相続税法の規定により遺贈等による財産の取得とみなされる場合を対象に含むとは規定されていないこと、②信託の帰属権利者は権利を放棄することができるから(信託法183③)、残余財産の取得を相続又は遺贈による財産の取得と同様に取り扱うことはできないとの理由で空き家控除の適用がないと回答した。
しかしながら、その内容は、いささか木を見て森を見ないもので、説得力に乏しく正鵠を得たものではない。そもそもこの制度は、朽ち果てる空き家を一つでもなくし、かかる社会問題を解消しようというところに法制度の考えがある。一方、家族信託は、加齢などで財産管理ができない高齢者の負担を少なくし、かかる者に代わって親族等が財産を適正に管理し本人の権利のみならず社会秩序をも守る法制度である。ともに大事な制度である。当局の見解を変えてほしい。
案件は自益型の信託契約で、母Aが所有する居住用家屋等を、受託者である子Bに信託譲渡し、Aが信託財産から利益を享受する受益者となった。この契約では、受益者の死亡により信託は終了し、居住用家屋等は相続人である帰属権利者のBとCの両名に給付された。
両名は、当該居住用家屋等を相続のあった年の翌年に売却したが、この譲渡について、空き家控除の要件である「相続又は遺贈により」(相法9の2④)、被相続人居住用家屋等の取得をした相続人に該当するから、空き家控除の適用があると考えるとして東京国税局に照会を行った。
しかし、東京国税局は、①信託の終了による財産の移転は単なるみなし規定で、「相続」や「遺贈」に該当せず、空き家控除の条文には相続税法の規定により遺贈等による財産の取得とみなされる場合を対象に含むとは規定されていないこと、②信託の帰属権利者は権利を放棄することができるから(信託法183③)、残余財産の取得を相続又は遺贈による財産の取得と同様に取り扱うことはできないとの理由で空き家控除の適用がないと回答した。
しかしながら、その内容は、いささか木を見て森を見ないもので、説得力に乏しく正鵠を得たものではない。そもそもこの制度は、朽ち果てる空き家を一つでもなくし、かかる社会問題を解消しようというところに法制度の考えがある。一方、家族信託は、加齢などで財産管理ができない高齢者の負担を少なくし、かかる者に代わって親族等が財産を適正に管理し本人の権利のみならず社会秩序をも守る法制度である。ともに大事な制度である。当局の見解を変えてほしい。
最近も、「実家信託」の相談を受けた。
委託者は、90歳で、施設に入所しているが、自宅は、父母の代から住まいにしていることから、まだ愛着がある。しかし、子供たちは、いつ朽ちるかと心配している。母が、判断能力が低下してからでは、売却できないし、預貯金も凍結されるので、家族信託を活用し、いつでも売れるようにしたいという。
私は、説明責任の中で、家族信託を利用すると、上記の特例が使えなくなると、リスクの説明をせざるを得なかった。
なんとも、家族信託支援業務を担う者に酷な文書回答なんだろうかと、恨んでしまった。
正しい信託 同期のサクラ 編
私は、テレビ番組『同期のサクラ』に凝っています。
私の趣味は、「桜の撮影」です。
特別印象に残った桜を選んで、自分の名刺に取り込んでいます。
名刺交換の際、皆さんのこころを読んで、桜の写真の入った十数枚の名刺の中から1枚を選び
お渡しする人に喜んでもらえるように心がけて、さりげなく名刺を渡ししています。
お渡しする人に喜んでもらえるように心がけて、さりげなく名刺を渡ししています。
それは別として、この番組は、「名言の宝庫」です。
家族信託に引用させていただきました。
●「まずい、ひじょーにマズい!!」
「家族信託は、何でもやりたいことを実現できるなどと言うのはまずい、ひじょーにマズい!!」
「家族信託は、二人で文書に署名すれば何でもできるなどと言うのはまずい、ひじょーにマズい!!」
「家族信託は、二人で文書に署名すれば何でもできるなどと言うのはまずい、ひじょーにマズい!!」
「家族信託は、登記すればあとは受託者がやりたい放題などと言うのはまずい、ひじょーにマズい!!」
●「・・・すると助かります」
「常識では、使えない信託を作らないでいただけると助かります。」
「多くの人の夢を台無しにする信託もどきけいやくの作成だけはやめていただけると、ひじょーに助かります。」
「裁判で、争いとなるような信託を作らないでいただけると、ひじょーに助かります。」
●「私には夢があります」
「私には夢があります。正しい家族信託を制作し多くの皆さんに使っていただくことです。」
「私には夢があります。一生信じて使える生きた家族信託を作ることです。」
「私には夢があります。家族信託で夢を叶えられたと、多くの人に言っていただくことです。」
成年後見制度は「ぬかり道」

私が生まれたのは、「宮城県名取郡愛島村」である。村の中心が笠島地区であるが、北部には光源氏のモデルとなったともいわれている藤原実方(中将)の墓がある。元禄2年(1689年)、松尾芭蕉が実方中将の墓を訪ねようとして、道に迷って詠んだとされる句がある。
笠島は いづこ五月の ぬかり道
笠島は いづこ五月の ぬかり道
いま、成年後見制度は、「ぬかり道」の中にある。
私は、被後見人本人に寄り添えば、自ずと意思決定支援はできる、指針やガイドラインは不要であるとの考えを持っている。そもそも「意思」とは何か、答えを出すのが難しいからである。しかも、時間が制約されている専門職に、本人に寄り添って、本人がいだいている考えや思いを本当に聞き出せるだけの心の余力があるのだろうかと思うと否定的にならざるを得ないのである。
しかし、最近、後見事務を5年間何もしない専門職後見人がいて、話題になっていることを知り、当然懲戒と解任事例だと思うとともに、かかる後見人をなくすために、強制的に本人に接して意思確認を求めるガイドラインがあってもよいかなと思うようになっている。情けない話だが。
だが、さらに考えてみるに、かかる職業後見人に正しい意思決定支援は望むことは無理であろう。お任せか、自分勝手の代行意思決定以上望めそうもないからである。
しかし、最近、後見事務を5年間何もしない専門職後見人がいて、話題になっていることを知り、当然懲戒と解任事例だと思うとともに、かかる後見人をなくすために、強制的に本人に接して意思確認を求めるガイドラインがあってもよいかなと思うようになっている。情けない話だが。
だが、さらに考えてみるに、かかる職業後見人に正しい意思決定支援は望むことは無理であろう。お任せか、自分勝手の代行意思決定以上望めそうもないからである。
正しい成年後見制度の実現は、道のりは遠い。しかし、やらなければならない。この「ぬかり道」から抜け出すには、本人にしっかりと寄り添える家族後見人と市民後見人の力を借りるほかあるまい。
正しい信託

法律、その他信託の基本的ルールを守り、公序良俗に反しない社会的にも認められる委託者の希望を叶える長期間機能する家族信託のことです。
言葉は単純ですが、奥が深く、一言では言い表すことが難しい意味を含んだ言葉です。
それは、依頼人の依頼内容に合致した、第三者から見ても公益的にも許容される目的と仕組みであることが必要だということです。
信託は、信託行為によって、それが何のため(目的)の信託か判ることが大事です。そして、それが信託法制をはじめ民法等の法律及び税制の面か も問題のない、依頼人を満足させる信託の仕組みになっていることが大事なのです。
正しい信託というのは、さまざまな視点から見て、依頼人からも常識的な依頼内容に沿って満足した内容であること、また第三者・専門家から見ても法制度(遺言相続制度、後見制度、福祉制度)に沿っており、また課税の面でも問題がないことを確認された信託であること、そして、それは「生きた信託」であること、「信託もどき約束事でないこと」ということでもあるのです。
それに、一般の人にも分かりやすい仕組みと表現になっていて、使いやすいものであることも要求されているとも言えます。 これが、私の言う「正しい信託」です。
「相続は早い者勝ち」 「遺言があれば安心」ということはなくなった!
相続改正法で、相続の効力等に関する対抗要件制度(民法899条の2)ができた。
第899条の2・1項によれば、「相続による権利の承継は、遺産の分割でも、遺言があっても、法定相続分及び代襲相続人の相続分の規定により算定した相続分を超おえる部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」となった。
(1) 遺産である不動産については、「相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)」とあり、相続人の一人が、法定相続分で、全相続人の分を登記することができるのである。
(2) 相続人の単独申請を回避する方法はない。
(3) 当該相続人の法定相続分について、第三者に処分したとき、遺言があっても、遅れれば、第三者に対抗できないこととなった。
民法899条の2の規定は、遺言制度を脆弱化する悪しき改正ともいえる。「遺産の分割によるものかどうかにかかわらず」とあり、遺言の相対的効力をもたらすこととなった。
「遺言があれば大丈夫。」と言えなくなったのである!
信託は、相続財産から消えるので、899条の2の問題は生じない。
相続人は、信託財産には手を出せないので、勝手に法定相続分の相続登記はできないのである。
一層、家族民事信託の重要性が出てきた。
「遺言より楽な家族信託」などはあり得ない
生きた信託
家族信託は、信託の長期的な管理機能を確実に働かせて、信託の目的を達成させることが大事です。
何十年もの間、制作した信託が機能するように細心の注意を払い、信託を制作することです。
この細心の注意を払って、できあがったのが、ここにいう「生きた信託」なのです。もちろん、長期の事務処理の中で、それが難しくなることがあります。その場合でも、目的に沿って迅速適正に信託が変更できる組み立てになっていることも大切です。
最初から課税問題で、頭をかかえて動けなくなった信託、第一次相続時、相続人から遺留分減殺請求がなされ信託行為が取り消されてしまうような、お粗末な信託によってもたらされる不具合のない信託のことです。
しかし、例えば受益者連続信託で、90年もの間、手を掛けず信託が生きることを望むことは無理があります。常に、事務処理や受益者保護のために、機能不全に陥らないよう、信託の変更を視野に入れておく必要があるのです。
「信託は魔法の箱」などではない
あざとい信託
これは、事例を見てもらえばよく判るでしょう。 拙書「家族信託契約」118ページの事案がそれです。
あざといという意味は、「抜け目がなく貪欲であること」です。それから、最近では、本例のように「まず常識人が考え及ばないような、自分にとって都合のよい手段で、相手が高齢者で自分の身を一切任せているというような弱みにつけて陥れる形で目的を達成する。自分だけが満足出きればよい」といった具合に、その行為が人道的にも批判されても知ったことではないという、意味にも使われているようです。
しかし、家族信託は 、受託者を利益させ喜ばすものではありません。受益者のための、財産管理であり、承継の仕組みです。法は、受託者が利益することを禁止しています。
(受託者の利益享受の禁止) 「第8条 受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない」のです。 本事例は、家族信託ではありません。単に、信託を模したあくどい生前贈与行為です。税当局は、黙っていないでしょう。
委託者は蚊帳の外
このことは、間違いだ、と登記に携わる専門職が言い始めています。
信託終了時の登記費用に関わる問題ですが、そのときの登録免許税が上手くゆくと減額(1000分の20が1000分の4)できるということからです。税額が、1000分の20と、1000分の4とでは、確かに出費に差はあります。
しかし、かかる話しは確かな信託、生きた信託があってこそ言えることです。信託の実務では、委託者の地位の承継は鬼門です。委託者の地位は、絶大です。受益者を変更できるだけでなく、信託を止める権限をも持っているのです。このため、信託法は、信託が開始すると、委託者の権限を全部剥奪して、かやの外に置くこともできるのです。
このことを忘れ、将来の課税のことで、角をためて牛を殺すようでは、信託を利用する意味がないともいえるでしょう。
この問題は、これから実務でどのような扱いをされるか、判りません。
拙書「家族信託契約」224ページの但し書の文言で、解決できないでしょうか。隠す信託登記 ― 相続前から「争族」が起きる
信託登記は、これを配慮しないと、ご本人が死亡する前から「争族」が起きる可能性があるのです。
信託登記は、登記された信託の内容を誰でも見ることができる制度になっているからです。その中に、相続財産(信託の権利)は「誰々に承継させる」「最後は、誰々に渡す」という、遺言に当たる部分も、登記することになっているのです。
そんな馬鹿なと、お思いになる人も少ないでしょう。
私も、5年前にそう思い、法務局登記官と戦った歴史があったのです。私は、信託契約は、実質は「遺言」だと思っています。だから、遺言部分は隠すことにしたのです。隠し方は、拙書「家族信託契約」に、詳細書かせていただきました。
私が戦ったのは、遺言を被相続人の死亡前から誰にでも見せるのはあってはならないことだという正義感からです。その事例は、不動産管理の信託契約で、登記する法務局は、4か所。
それぞれ、この「隠した信託目録」の登記申請書を作成して、まず、宇都宮の法務局に出しました。「そのような申請書は見たことがない」という理由で、受け付けもらえず、次に、東京法務局の支所に出したのですが、ここも「表記の仕方不十分」という理由でアウト。次は、千葉法務局支所、登記官には、「遺言を誰でも見ることができる仕組み」を公務員が無神経にすすめるのは、個人情報を漏らしているのと同じではないか、というスタンスで説明したところ、それが運よく理解してもらえたのです。そこで、その謄本を手にして、宇都宮の法務局、次に東京の法務局支所に赴き、考えを変えてもらったのです。
こんな歴史があったなという思いが、今も鮮明に残っています。
宙に浮く信託財産
家族信託契約を知るうえで、信託がいかに特異な法的な仕組みかを確実に会得する必要があります。
そこで、頭に入れていただく大事な事項は、信託に組み込まれる財産(信託財産)が、本人のものでなくなり、本人の遺産から消えるということです。
この信託財産は、これを託された受託者の名義になりますが、「誰のものでもない財産」(nobody’s property)として信託の中で扱われるということです(「新訂 新しい家族信託」34、95ページ)。
そこで問題になるのは、「倒産隔離機能」です。
一般的には、考え方は同じになろうかと思います。ただし、考え方はさまざまです。委託者がすべての権利(受益権)を持った当初受益者の場合は、倒産隔離は働かないという、有力説があります。 この考え方からすると、自益型自己信託 (私の考えでは、そもそも「無効」) にあっては、倒産隔離はまったく働かないということです。
成年後見制度を知らないで家族信託は組成できない
信託もどき口座
「なんちゃって口座」と同義語。
これは、民事信託管理口座として「倒産隔離」を有しない普通の預金口座のことです。
この口座では、何が起こるかと言うと、「受託者の相続人が歓喜する(泣いて喜ぶ)預金」の口座になるのです。実際に起きているので、恐ろしい口座になるのです。
銀行の預金 (普通預金) は、基本的には、預金者本人の名義の口座名が付されます。これが、倒産隔離のない「信託口座もどき」の受託者の名義では、受託者が死亡したときは、受託者の固有財産として扱われるのです。したがって、受託者が死亡したとき、当該預金は死亡した受託者の預金として扱われ、凍結されます。そこで、その相続人が遺産分割協議書を作成し、銀行に提出してその預金を払い戻しすることができてしまうのです。もちろん、受託者に個人ローンがあれば、相殺されてしまい、信託関係者は、青くなってしまうほかありません(実際は、受託者の相続人が喜んで泣く預金なのです)。
「屋号口座」もその一種、信託口座とは扱われない「受託者」の固有財産となる「預金の口座」になります。これは、倒産隔離機能がありませんので、受託者が死亡しますと、受託者の相続財産として扱われ、相続人が、払い戻しできることになるのです。
あとは、裁判と信託組成者を責任追及するのでしょうか。
信託もどき契約 (信託もどき約束ごと)
千年信託(未来永劫信託)
家族信託の歴史が消える
国民から、信託はまがいものの法律制度という、レッテルをはられて、この世から消えてしまうことです。
私は、「新しい家族信託」のあとがきに「信託であるとして何もかもできるわけではない。ときには、信託が禁止されたという歴史があることを振り替えてみることも必要である。」と書かせていただきました。 反トラスト法もその一つです。反トラスト法とは、信託 (トラスト) などを禁止・制限する法律のことです。
それが、私の強いその思いです。要は、信託もどき困った信託を作りあげて、使えない信託を世に出すことによって、国民の信頼を失なってしまうことだけは避けたいのです。
信託もどき契約は、世の中に出してはならないのです。
盗っ人信託
成年後見制度では、後見人の使い込みが、大きな社会問題となっていますが、信託も、同じ財産管理制度であり、受託者は、自分の利益のために信託の仕組みを悪用は出来ません。
家族信託では、受託者の横領や背任行為は、許容しません。
「盗っ人信託」の例は、「受託者は、信託不動産の管理上適当と判断したときは、信託財産である不動産を受託者の固有財産に帰属させることができる。」というような、信託の条項にあってはならない定めです。
私は、かかる信託条項は犯罪的行為を唆すあるいは下支えする、刑法で言う「幇助罪」にあたるような定めであり、これが受託者の不正を助長する、ひどいものだと思っています。これが公正証書でできあがっているので、あぜんとしてしまいます。
「横領信託」「背任信託」 も同じです。
要は、犯罪的な公序良俗上認められない信託設定は絶対にやるべきではないのです。ワンストップ信託
これは、この連結した特殊な機能を活かすことによって、その目的を達成するものであり、一つ一つ分断させては意味がない。初歩的なミスとは言わないが、後見的財産管理機能だけを利用して信託はやめて、残余財産は遺産分割に委ねるというのでは、これを利用する意味がないともいうべきことだと思う。